【勇気をもらった南米ペルーからの手紙】
東京女子医大から母校の慈恵医大に帰ってから、2年後の1974年(昭和49年)南米のペルーから1通の手紙が届いた。それはリマで開かれる第19回、国際外科学会のパネリストに採用されたという通知であった。1971年、恩師・榊原先生は定年を迎えられ、次の主任教授選挙が行われた。私も立候補したが、選挙の結果、私より7歳若いK先生が主任教授に選出された。その時から私の心臓血圧研究所での定位置は失われ、女子医大を去らなければならなくなった。私は、人生の“どん底”に落ちた感じであった。
私の落選を知って、慈恵医大の2、3の先輩の間から『新井をこのまま潰してしまうのは勿体ない。』という小さな声があがった。この声は少しずつ大きくなり、当時の慈恵医大学長・樋口一成先生の耳に達し、母校・慈恵医大に帰る道が開かれた。そして道が開けるとともに、“どん底”にあった私も少しずつ這い上がって行った。
こうして1972年、慈恵医大に帰った私は、第1外科の定員外教授として心臓外科を担当した。その翌年に、心臓外科は特設診療科として第1外科から独立した。私は独立して、心臓外科の医局、外来、病床ベットを持つことができたことを、喜ぶとともに神に感謝した。しかし、医局員は、2年間の研修を終了したばかりのM君とH君、それに人工心肺の操作の経験のあるS君の4人であった。
手術成績は良好で、100例のうち99例が成功した。その中には、ファロー四徴症や人工弁置換手術も含まれている。患者さんは増えて来たが、3人の医局員では仕事量に限界があった。私の窮状を知って、T医大、K医大とJ医大の教授は1人ずつ医局員を派遣して下さった。私は涙のでるほど嬉しかった。また、女子医大・心研から頑張り屋のK君が入局してくれた。
このように心臓外科の医局が発足して間もないときに、ペルーからパネリストに採用するという朗報がもたらされた。“どん底”より立ち直りつつあった私は、これに勇気を得て、“私たちの医局を日本の一流のレベルにし、世界に通ずる心臓外科の教室にしよう”という夢を抱いた。
【お土産に“味の素”】
リマの学会に出席するドクターとその家族、約30人で旅行団が結成された。その旅行日程によると、ペルー・リマの国際外科学会に出席後、アルゼンチン、ブラジルを訪問したのちに帰国というスケジュールになっていた。そこで、私はブラジルに行くのなら、私の生後2年間、病弱だった母と一緒に私の世話をして下さったのち、ブラジルに移民した看護婦のTさんの墓参をして、昔の感謝とお礼を言いたいと考えた。日程表によるとお墓のあるサンパウロにも3泊することになっていた。そこで、Tさんの家族に何か“お土産”を持って行こうと思い、家族といろいろ相談して“味の素”にすることにした。これなら、旅行中に傷むこともなく、Tさんの家族に日本の味を味わっていただけると思い、2kgの味の素の袋を2袋持参することにした。当時の旅行用トランクには、移動用の小さな車は無く、トランクは腕で持ち上げて運ぶものだった。4kgの味の素は相当の重量であったが、Tさんの家族に喜んでいただけると期待して、この重さを我慢した。
【地の果てに来たのか】
ペルー・リマの空港から、専用バスで市街地に向かった。空港から市街地までの道路の両側は丘陵状の山々で木も草もなく、乾き切った黒褐色の山肌が露出しており、屋根のない掘っ立て小屋があちらこちらに点在していた。まるで地の果てのような、こんな荒野に来なければよかったと後悔するほどであった。1時間くらい走ったであろうか? 左側に大きな工場が現れた。近づくと、その工場の壁面いっぱいに何と! “味の素”と赤い大きな日本文字が書かれていた。エッ!! ペルーに味の素の工場があったのか!? それを私は全く知らなかった。きっと、ここから南米全土に味の素は販売されているであろう。考えに考えて、南米では貴重品と思ってお土産に選んだ“味の素”の価値は無くなってしまった。私はがっかりすると同時に、トランクが急に重くなったように感じた。
市街地に入ると,道路の左右には街路樹が植えられていた。その街路樹は根元から1mくらい白い塗料が塗られていた。虫よけの薬剤らしかった。道路の両側には5、6階建てのビルディングが並んでいた。添乗員の説明によると、これらのビルは鉄筋コンクリート建てではなく、土を固めて作ったアドベ 注)で建てられている。リマは1年365日雨が降らない土地なので、アドベの建物で大丈夫だという。ホテルは日本の2流か3流のホテルで、玄関を入るとロビーの正面にインカ帝国の遺跡マチュ・ピチュの大きな壁画がアンデス山系の緑の山々を背景に飾られていた。
注)アドベ(adobe); 粘質の土を焼かずに天火だけで乾し固めたレンガ。降雨の少ない地域で用いる。日干し煉瓦。
【学会の開会式】
学会場はアドベで建てたのだろうか? 立派な5階建ての建物であった。開会式が行なわれるので、私は恩師・榊原先生と式場に入ろうとすると、係の青年が「入場するなら、この箱にパスポートを入れて下さい」と箱を差し出した。先生と私は「パスポートのような大切なものを預けられるか!」と、学会の名札を入れて会場に入った。
開会式は始まっていた。恰幅のいい10人くらいの役員が演壇上の椅子に腰をかけ、つぎつぎにスペイン語かスペイン語なまりの英語で挨拶をした。私たちにはほとんど分からないスピーチだった。榊原先生はノートを取り出して、壇上の役員の似顔絵を書き始めた。先生は、二科展に4度入選した経歴のある絵の大家である。先生の似顔絵は、頭の剥げた太った人、痩せぎすで顎のとがった人など本当によく似ていた。1人を5、6分で画くので、笑いをこらえながらその絵を見ていた。
公式サイト
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=284&language=en_USより
【学会始まる】
翌日の午前、私のセッションでの第1席はソ連のMeshalkinで、低体温法による心室中隔欠損症(VSD)の映画を公開した。第2席はクリーブランド・クリニークで冠動脈のACbypass術を世界に広めてから故郷のアルゼンチンに帰った、世界で有名なFavaloroの講演で,超低体温法による先天性心疾患の手術について発表した。第3席はブラジルのZerbiniで人間の脳硬膜を用いて心臓の生体弁を作り100例の大動脈弁置換と僧帽弁置換に使用し、6例の死亡はあるが、血栓症の発生は皆無であったと報告した。第4席は私で、世界最長生存例のA型単心室の手術手技の要点と術後の経過を報告した。第5席は榊原先生で日本における心室中隔欠損症(VSD)の形態と、大動脈弁の石灰化に日本と欧米では差異のあることを報告した。第6席ヒューストンのNoonは大動脈瘤の手術について報告した。その後、約30分、各演題に対して質疑応答が行われた。
午後は冠動脈のACbypass手術のセッションであった。先ず、クリーブランド・クリニークのLoopが多数例の成績と予後を報告し、ついで、アルゼンチンとブラジルの現況が報告された。南米でもACbypass手術は盛んで,アルゼンチン、ブラジルでは1000例以上の手術が行なわれ、死亡率は7%で、最近はグラフトとして内胸動脈を使用し、開存率は98%と報告している。この発表の時点では、日本は米国、南米に数年遅れていた。
【ジャパニーズ・レストラン】
この夜、榊原先生と日本料理店に行こうということになった。榊原夫人は2泊3日でマチュ・ピチュへ行くオプショナル・ツアーに参加していた。私もこの旅行に参加したかったが、丁度、学会発表の日と重なって、残念だったが断念した。
【成功した日系2世の家に招かれる】
翌日、ペルーの日系2世が榊原先生を訪ねてきた。先生が日本で何度か診察した患者さんであった。その夜、先生と私は彼の家に招待された。リマの中心部にあるマンションのワンフロアーが彼の住居であった。話によると彼の父親が、苦労して財をなしたのだという。彼の奥さんは10年くらい前に日本から嫁いで来た方だった。応接間は30畳、食堂は20畳くらいの、ガラスで仕切られた豪華な住まいであった。そこで、夫人の手料理をご馳走になった。それは、昨日とは全く異なる本格的な美味しい日本食だった。
【ペルーでゴルフを楽しむ】
その夜、急にゴルフに誘われた。その翌朝、彼の車でゴルフ場に向かった。1年中、雨の降らないリマだから、土の上でプレーするのだろうと余り気が進まなかった。しかし、ゴルフ場に着くと、想像とは全く違って、青々とした緑の芝のフェアウェーが広々と広がっている。日本の一流のゴルフ場並みの手入れがしてある。フェアウェーの外側には古代の遺跡のような建物が半壊状態で立っていた。思いがけない立派なゴルフ場で、ゴルフのクラブと靴を借りて1日ゴルフを楽しんだ。アンデス山系の水を引いて、十分な管理を行なっているのだという。
ペルーに到着したときは地の果てに来たのかと思うほどの貧民街を見たが、旅の終盤は、ペルーのブルジュア階級の人にもお会いした。ペルーは日本では想像できない貧富の差の激しい国であった。
-scaled.jpeg)

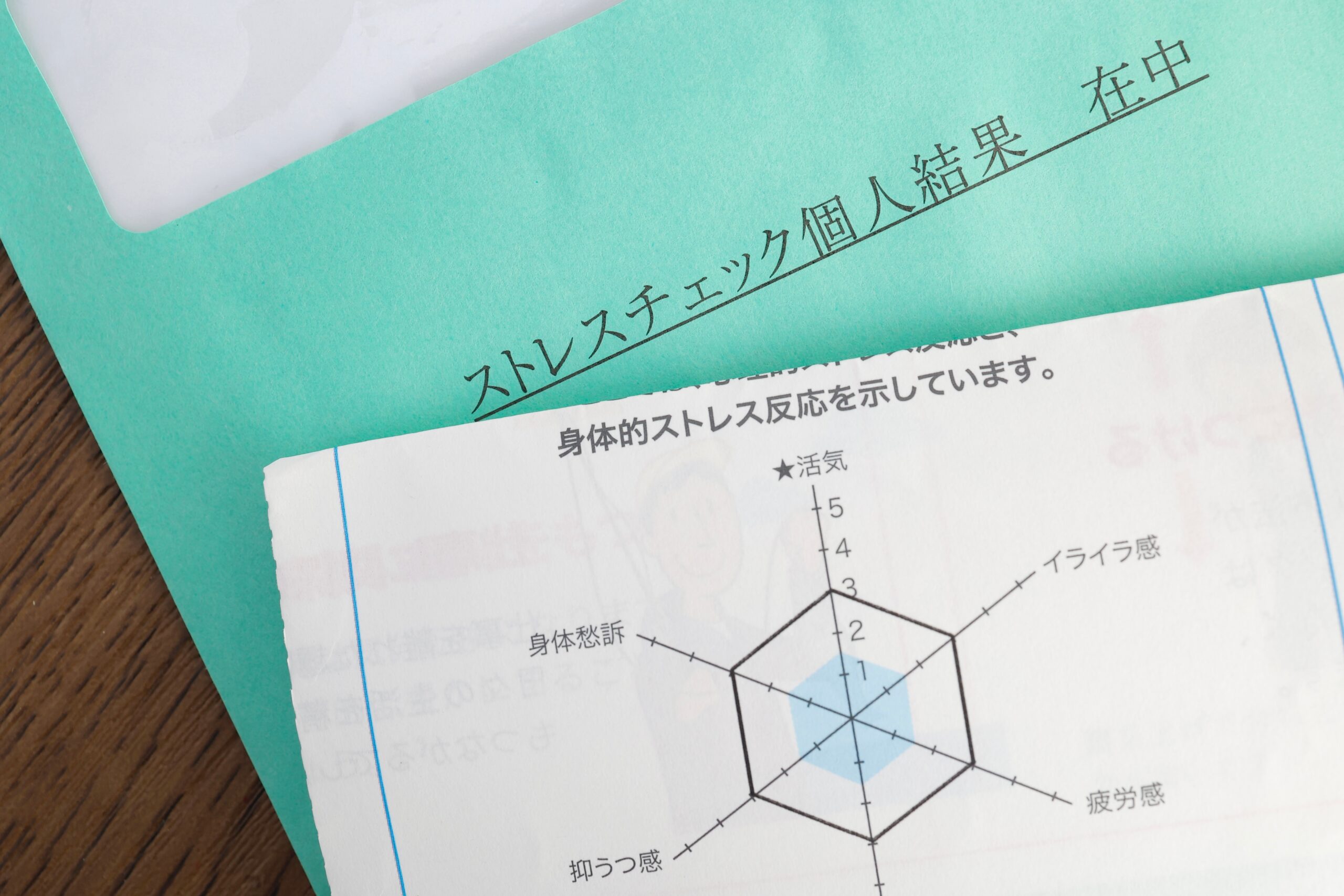


-scaled.jpeg)
